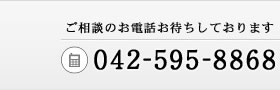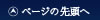理事長挨拶

近年、結核菌群特異抗原が発見され、BCG接種の影響を受けない新規結核感染診断法が開発されました。このような新規の結核感染診断法の適用範囲ないしは有用性を研究するためには、広域的かつ組織的な共同研究が必要となります。2004年(平成16年)8月、本研究会の前身となる結核感染診断技術研究会が東京千代田区三崎町の財団法人結核予防会水道橋ビルでクローズの会として発足しました。
ほぼ1世紀に亘り、結核感染の診断法として唯一ツベルクリン反応(ツ反)が、全世界で使用されてきました。しかし、ツ反で使用するPPDは、結核菌の培養ろ液を加熱滅菌し、タンパクを沈殿させて調製したもので、数百種類もの結核菌抗原が混在し、その殆どのものがBCGあるいは非結核性抗酸菌の抗原と高い類似性を持つため特異性の点で重大な欠点を持っています。
それはBCG接種や非結核性抗酸菌感染でもツ反陽性結果を導き出します。
このため、BCG接種が広範に行われている日本では、ツ反による正確な結核感染診断は難しい点が多く、この点を克服した新規結核感染診断法が、近年の結核菌遺伝子解析技術の進歩に伴って開発されました。
その方法はInterferon-gamma release assay(IGRA)と呼ばれるもので、現在多くの国々の結核診断の場で使用されています。
このIGRAに採用されている抗原はESAT-6と CFP-10と呼ばれる結核菌抗原で、これらを使った検査としてQFTとT-SPOT.TBの二種類の手技が開発されています。
QFTが国内に導入される事が明らかになった時点で、明確にしなければならない幾つかの課題の研究と、正しい検査技術の普及を目的として結核感染診断技術研究会を発足させました。この研究会はクローズかつ任意の会として7年間(第7回が最終会)続けられ、その間に、感染源への曝露の時期から結果が陽性になるまでの時間経過や長期間における応答の消長、あるいは化学予防や化学療法の影響など、さまざまな状況に置ける診断特性について研究がおこなわれてきました。しかし、小児、特に乳幼児の特性や免疫脆弱者における研究は、クローズの会で在ったが故に各分野の専門家との協力体制が整わず、次第に研究成果に偏りが出るように成って来ました。
会員からもオープンな研究会にして研究成果を広く募るべきとべきとする意見が出始め、そうした機運の中、2010年(平成22年)の第7回の研究会において会員総意のもとに、広く情報発信・社会貢献を基盤とするNPO法人格を取得した研究会を創立すべく結核感染診断技術研究会を発展的に解散し、結核感染診断研究会に移行して2012年(平成24年)に特定非営利活動法人結核感染診断研究会を創設しました。
特定非営利活動法人結核感染診断研究会(Specified Non Profit Corporation Research Institution of Tubercle Infection Diagnosis : RITID)は、公的な研究会としてIGRA検査の外部精度管理を遂行し、同時に解明しなくてはならない研究課題と結核対策に貢献でき得る研究を積極的に推進し、そこに集積した情報を会員各位に発信・討議しながら、結核感染診断技術の改善・改良に対して公的な立場で提言を行って参りたいと存じます。
また会員以外の方々にもホームページを通じて結核対策の重要性をお示しできるような活動の実施を考えております。
さらに将来的にはこの研究会で集積した知的財産や技術を結核高蔓延国にも提供し、対策に活かせるような協力体制を構築してまいりたいと思います。
日本国内の新登録結核感染者が(10万対率)10を切る日が1日も早く来る様に、本研究会正会員の皆さまの御尽力と賛助会員の皆さまの御支援を頂き研究会活動の活性化に取り組んでまいります。
広く皆さまの御支援御協力を心からお願い申し上げ 理事長挨拶とさせていただきます。